よこみち【世読】No.8「亡者の集い」
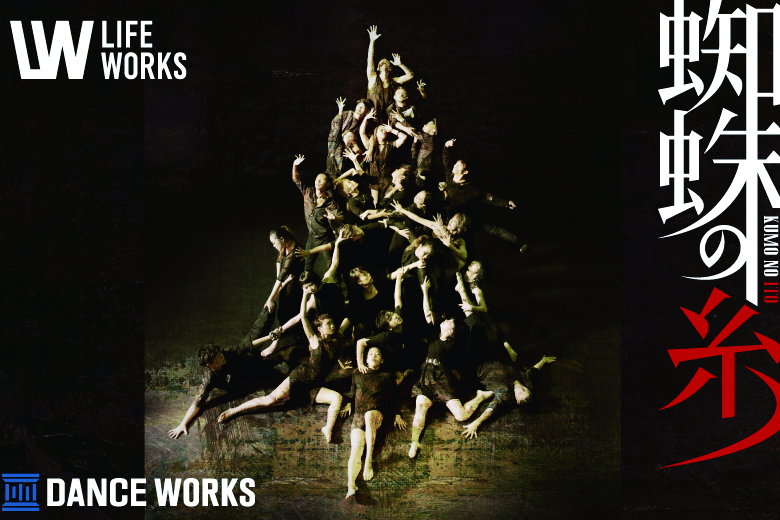
このたびの「参(サン・まいる)」だがちょっと見てみるとかなりツッコミどころの間口が広いもののようだ。
たとえば和語としての「まいる」。どこそこへまいる、という本編の言い方のほかに、すぐ思いつくのは「いや~、まいっちゃったよ」という言い方。他にもいろいろありそうだが、そのあたりはちゃんと辞書がカバーしている。詳しい紹介は省くけれども、元来は貴人のところへ下位の者が行くことを言う謙譲語だったものが、だんだん敬う意が薄れてきて「まいっちゃったよ」という方向へ語義が流れていったものらしい(『日本国語大辞典』「まいる」項参照)。
これに対し漢語の「参」。『諸橋大漢和辞典』によれば、
一、1)みつ(三)、2)三者立ちならぶ、3)たちならぶ、4)まじはる、5)あづかる、6)かねる、7)こもごも、8)まうでる、9)~18)略。
二、1)星宿の名、2)ながいさま、3)斉しくないさま、4)鼓を撃つ法、5)人参、6)姓。
三、1)多くのものがしたがひつづくさま、2)略。
とその語義はまた多様である。ここで和語と漢語のちがいを取り上げるのも一手なのだが、それよりも気になることがある。
それは『世説故事苑』が、参の意について「謂く幽顕皆な集まり神龍並び臻(いた)る。既に聖凡間(へだ)つること無し豈に輙(たやすく)僧俗を分たんや。ここを以てこれを参と謂う」と結論づけている点である。これは『世説故事苑』自身が言うように『祖庭事苑』巻八を典拠としている。この本は宋代の禅語辞典と言えるもので、この中の「小参」という項目にこの文章がある(じつは日本の無著道忠による『禅林象器箋』が「小参」について同じ引き方をしているので、子登はこっちを見たのかもしれないけどここではどっちでもかまわない)。
これの何が気になるのかというと、「幽顕皆な集まり神龍並び臻る」というところなんだ。これはつまり「幽顕」すなわち幽界(あの世)の者も、顕界(この世)の者も、さらには人間ならぬ神龍たちも群れ集まってくる、という意味じゃないだろうか。それが「参」だというのである。この解説はさきほどの『日本国語大辞典』にも『諸橋大漢和辞典』にも見えないものだった。すでに見たように子登のオリジナルでもなく宋代の禅籍に見えるものだ。はたしてこれを「参」の中国的理解だとか、インド以来の仏教的発想によるものだとか言っちゃっていいのかどうか解らない。もしかするとすでにこれについて調べている人があるかもしれないけど、いまのところそっちは当たっていない。
でもおもしろいなと思う。
どうしてここで「幽界」のことまで引き合いに出てくるのだろう?
『祖庭事苑』の立項には(『世説故事苑』に見たように)早參・晚參・小参を出し「是皆以謂之參」とするが、ということは禅僧の力に関わるものなのだろうか?
そう考えると和語と漢語の語義の拡がりよりも、なにか奥深い「参」の意味にたどり着きそうに思うのだが、残念ながら今の時点ではここまでの思いつきで「まいった」と言うしかない。
乞う、賢者のご教示を。
【世読】No.8「参(サン・マイル)」巻一〈倭文用語類〉(web読書会『世説故事苑』)

これも禅家より出たり。禅家に朝の上堂を早参と云い、暮に看経するを晩参と云い、不時に説法するを小参と云う。総じて和尚に拝謁して法を問うを参ずると云う。
今俗に彼(かしこ)に到るを参すると云い、参(まいる)と云うこれに依ってなり。参の字義はまじわると云う義なり。故にまじわりにいたると云うを中略して参の字をまいると読せたり。[この訓正しく参詣の二字なり]次下に引く『事苑』の釈を見ばこれ等の義善く会すべし。
○『祖庭事苑』八に曰く。「禅門詰旦に昇堂す、これを早参と謂う。日晡に念誦するこれを晩参と謂う。非時の説法これを小(しょう)参(さん)と謂う。それこれ皆な以てこれを参と謂うは何ぞや。曰く“参の言為(ことたる)それ広くして且つ大なり。謂く幽顕皆な集まり神龍並び臻(いた)る。既に聖凡間(へだ)つること無し豈に輙(たやすく)僧俗を分たんや。ここを以てこれを参と謂う」。
よこみち【世読】No.7「ちんぷんかんぷん」

挨、拶、いずれも一対一で禅僧が相対した時、相手の禅機をはかるところから生まれた語。この本編の解説は、ときに一見意味の通じにくい仕草や言葉を交わすこともある禅問答を踏まえているものだ。
落語「蒟蒻問答」は、禅問答のちんぷんかんぷんさをパロディにしたものだが、あらためてこの話を聞くと、これはかなり秀逸なものではないかと思う。
仲間を募って毎月一度『碧巌録』を読んでいる。入矢義高先生の岩波文庫本をテキストに、末木文美士先生の現代語訳とともに、そして小川隆先生の禅語録に関する著作を参考にして読んでいる。訓読文であり、現代語訳であり、しかも詳細な註があるのだからよくわかる・・・かと言えばさにあらず。情けない話だが、一つの文章をわかるまでにはかなりの難儀をしている。正直に言えばよくわからないまま読み飛ばすことも往々にしてある。垂示・本則・着語・評唱・頌・着語・評唱。各本則をめぐると雪竇と圜悟のバトルに翻弄されっぱなしだ。それでも時に評唱の説明がすっと入ってきたり、入谷先生たちの訳語や解説にうなずいたりという(決していつもそうだとは言わないが)腑落ちの経験がこの会を持続する支えになっている。
しかし日本に禅語録が伝わって以来、現代に至るまでほとんどずーっと「誤読の伝統」が維持されてきた、と入谷先生は言う。詳しいことや実例はそれぞれの先生達の著作に豊富にあるのでここでは省略するが、精緻な研究の成果に接して私も「きっとそうだったんだよな」と思う。これに乗っかって誤解を怖れずに言えば、日本の禅宗における禅語録理解というのは、わかっていないものがわかっていないものにわかっていないことを伝え続けてきた、と言えてしまうのではないというくらいおそろしい状況にあったのだと思う。今初めて私たちはこうした先生達の手引きによって禅語録本来の意味に向きあい始めたと言えるのかもしれない。
そんなわかっていないものがわかっていないものにわかっていないことを伝えているという禅僧のウソを、「蒟蒻問答」の作者は(禅問答の内容を察知していなかったとしても)見抜いていたのだと思う。永平寺で修行し諸国行脚中だという禅僧・托善も、住職になりすました蒟蒻屋の六兵衛も、わかっていないという点では同じ穴のムジナ。それをこの落語は痛快に笑い飛ばすが、じつは当時の禅僧達への痛烈な皮肉でもあったのだ。
【世読】No.7「挨拶」巻一〈倭文用語類〉(web読書会『世説故事苑』)

これ禅家の語なり。禅家に一機一言にて来者の胸中を試むるを挨拶と云う。俗に客に対談するを挨拶と云はこれに依ってなり。
○『碧巌集』三に曰く。「玉は火を将(も)って試み、金は石を将って試み、釼は毛を将って試み、杖は水を将って試み、衲僧門下に至っては一言、一句、一機、一境、一出、一入、一挨、一拶、向背を見んことを要す」[文]
『篇海類編』八に云く。「挨は鴉蟹の切、音は矮、推なり。また撃(たげき)なり。また拶は姉末の切、声は雑に同。逼拶なり。譌(あやま)って拶に作る」[文]然れば、挨拶とは推(すい)撃(きゃく)逼切(ひっせつ)して彼が胸襟(きょうきん)を勘破する意なり
よこみち【世読】No.6「最期のごちそう」

三国時代、呉の人孟宗は筍好きの母親のために冬山の竹藪に筍を求めに入る。しかし雪の中に筍はない。落胆と悲しみに天を仰ぐ孟宗に感じて、天が筍を与えたと伝えられる。
こと大切な人のために少しでもよい食材を用意したい、そのためにできる限りの手を尽くした人々のエピソードは多い。パーヴァー村の鍛冶屋チュンダもその一人。
八十歳を迎えようとしていた仏陀は、アーナンダを伴い最後の旅に出る。年老いた身体を引きずり、霊鷲山(王舎城)から故里の北に向かってガンジス河を越え、行く先々で布教・伝道をしながらの旅であった。「 若き人アーナンダよ」とよばれるアーナンダの年齢も五十歳を超えている。
途中のパーヴァー村では鍛冶工の子チュンダに法を説いた。喜んだチュンダは、釈尊を次の日二月十五日の朝食に招待する。ところがチュンダが心をこめて作ったきのこの料理は、釈尊の弱った身体には合わなかった。釈尊はすぐに気がついたが、チュンダの好意を無にしたくなかった。それとなく他の者には食べさせないようにチュンダに話した。
しかし、食した釈尊は激しい腹痛と下痢と出血に苦しむ。ところが、釈尊はクシナーラーを目指して再び出発するのである。今夜が最後の夜と覚った釈尊は、カクッター川の川岸で休まれ沐浴をした。
川岸に横たわった釈尊はアーナンダにことづてを頼む。チュンダが、「 自分の供養した食べ物で釈尊が亡くなった」と思って苦しまないようにという配慮であった。
きっと誰かが、「 チュンダの料理のせいで釈尊は亡くなられたのだから、チュンダには利益がなく功徳がない。」と言い出すだろう。しかしそれは間違いで、私はチュンダの料理を最後の供養に選んで逝くのである。
私の生涯で二つのすぐれた供養があった。この二つの供養の食物は、まさにひとしいみのり、まさにひとしい果報があり、他の供養の食物よりもはるかにすぐれた大いなる果報があり、はるかにすぐれた大いなる功徳がある。
その二つとは何であるか?
一つはスジャータの供養の食物で、それによって私は無上の完全なさとりを達成した。
そしてこの度のチュンダの供養である。この供養は、煩悩の残りの無いニルバーナ(涅槃)の境地に入る縁となった。
チュンダは善き行いを積んだ。
奔走・馳走の「走る」は、文字通り走り回るというよりも、食材を用意する人の心の用いようを形容する言葉だろう。その心づくしに深く感謝することばが「ごちそうさま」だ。
チュンダの釈尊に対する心づくしは、釈尊のチュンダに対する心づくしにつながり、その釈尊の心は遠い時を隔てて今の私たちの心を動かす。
【世読】No.6 「奔走」巻一〈倭文用語類〉(web読書会『世説故事苑』)

客を饗応(もてなす)を奔走と云う。奔り廻りて供具等を弁する意なり。馳走と云うも同じ。
○『書』の「武成」に云く。「駿(すみやか)に奔走して籩豆(へんとう:食物を盛る器)を執る。」
よこみち【世読】No.5「珍獣」

はたして『世説故事苑』選者の子登は知っていたかどうか、禅宗で「珍重」と言えばまっさきに思い浮かぶのが法戦式の場面だろう。結制安居のクライマックス。座中より選ばれた首座和尚相手に、血気盛んな修行僧達が語気も鋭く次々と法問を挑んでくる。それをちぎっては投げちぎっては投げのアクションヒーローよろしく、気迫に満ちた報答で応じてゆく首座和尚。まさに結制修行の花形場面。禅宗のお坊さんなら誰もが経験している場面だろう。
いく度かの問答の最後、問者は「珍重(ちんちょう)」と結ぶ。〈すばらしいお答えをいただきました。どうぞこれからのご修行もお体に気をつけて無事の円成を迎えられますことを〉という気持ちを含む。これに対して首座和尚の結びは「万歳(ばんぜい)」。〈ありがとう。あなたと問答を交わすことによってここに一つの禅の教えを現成することができた。しっかりがんばります、あなたもどうぞお達者で〉という気持ちを含む。(※どちらもかなり盛ってますが)。この「珍重」「万歳」をいくつも重ねてゆくのが法戦だ。
さてあるご寺院で法友の結制式に随喜した。その法戦式に臨んだ時のことである。
首座和尚は僧堂安居中ということで威儀進退も凜としたもの。精悍な容貌も相まって、並み居る若い僧侶達と交わす法問の応酬も充分な気迫がみなぎっていた。何人目かの問者の時だった。畳みかけるように交わす法問の最後、問者が言った結びの言葉は法堂に詰めかけた大衆の誰もが聞き慣れない言葉だった。
「ちんじゅう」。
いったい何が起こったのかとっさに判断できないまま、それでも首座和尚は法問のシナリオを進めなければいけない。
「万歳~!」。
やや遅れて堂内はちいさくどよめいた。コトの次第に気がついた座中の僧侶達はおそらくみな思ったに違いない。〈珍獣???? いや、どうして誰も事前に教えてあげなかったのだろう〉と。
註1:この話、盛っても作ってもおりません実話でございます。
註2:この話、失敗したことを茶化したり笑おうとしたりするものではありません。法要に臨む周到な準備の大切さを、誰よりも私自身再認識するためのものでございます。